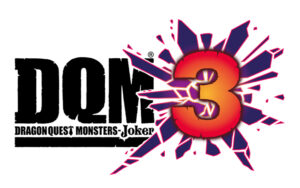九日ナインソールのボス攻略について調べている方に向けて、全ボスの立ち回りの要点や序盤から終盤までの攻略チャート、攻略マップの見方、玉石の選び方、稼ぎやレベル上げの考え方までを横断的に整理します。蚨蝶やせつぜん、風氏、易公など詰まりやすい相手の攻略も、要点を分解して言語化します。真エンドの到達に関する前提要素も触れます。各章は箇条書きに頼らず手順を文章で説明し、実戦で再現しやすい知識に落とし込みます。
この記事では、ボスの攻略だけでなく、攻略チャートに沿った進行、攻略マップの把握、玉石の構成、稼ぎとレベル上げの優先順位など、検索意図に沿う情報を一つに集約します。特に易公の攻防や風氏の第2形態、蚨蝶の分身処理、せつぜんの事前弱体化など、仕組みを理解して対処できるよう丁寧に解説します。
【この記事で扱う主な要素】ボスの攻略、チャートの組み立て、真エンドに関する前提、蚨蝶やせつぜん対策、易公の行動整理、攻略マップの見方、玉石の使い分け、風氏の第2形態、稼ぎとレベル上げの考え方
- ボスごとの要点と汎用的な対処の型を理解できる
- 攻略チャートと攻略マップの活用方法が分かる
- 玉石の推奨構成と稼ぎやレベル上げの優先順位を掴める
- 真エンド到達に向けた前提要素と注意点を把握できる
九日ナインソール攻略 ボスの基礎知識
- 攻略チャートの流れ
- 攻略マップ活用術
- 玉石のおすすめ
- 稼ぎの効率化
- レベル上げ指針
攻略チャートの流れ
序盤から終盤までの流れを俯瞰すると、各ボスは新しい操作や判断を学ばせる配置になっています。序盤は英招でパリィと無量弾きの基礎を反復し、中盤は勾芒、刑天、奄老、康回などでギミック処理や距離管理を学習します。終盤はせつぜん、蚨蝶、姫、風氏、そして易公へと進み、入力の精度と選択の速さが求められます。手詰まりを感じた場面では、先に対処の型を練習してから再挑戦することで、進行が安定します。
行動合図は全体を通して一貫しています。音による予兆、赤攻撃の視覚的シグナル、攻撃前のタメ動作など、見落としやすい手がかりを拾うだけで被弾が大幅に減ります。特に赤攻撃は無量弾きまたは回避のみで受ける設計が多く、最初に「赤=パリィ不可」と頭に固定しておくと判断が早まります。
矢は多くの戦闘で行動を中断させる切り札として機能します。弾数管理と補充手段をチャートの前提に置くと、連戦でもペースを崩しにくくなります。補充の導線をボス前エリアの往復に組み込み、矢は危険行動の初動に限定して使うことで、安定度が上がります。
終盤の分岐や真エンドを見据える場合は、NPCイベントや収集要素を並行管理する計画性が求められます。イベント依存の扉やタイミング限定のフラグは、ストーリー進行と探索のバランスを崩さない範囲で優先して回収しておくと、やり直しの手戻りを避けられます。
フェーズ別の到達目安と学習テーマ(参考表)
| フェーズ | 主なボス例 | 学習テーマ | つまずきやすい要素 | 先に身につけたい型 |
|---|---|---|---|---|
| 序盤 | 英招 | パリィと無量弾きの基礎 | 赤攻撃の見極め | 赤=回避または無量弾きの固定化 |
| 中盤 | 勾芒・刑天・奄老・康回 | ギミック処理と射撃介入 | 連携ギミックでの視野不足 | 危険行動の初動に矢で中断 |
| 終盤① | せつぜん・姫 | フェーズ管理と強化解除 | 回復やバリアの対処遅れ | 溜め攻撃でのバリア破壊と阻止 |
| 終盤② | 蚨蝶・風氏 | 多体・多段圧力の整理 | 分身の誤認と同時圧力 | 本体へのスタン起点で盤面整理 |
| ラスト | 易公 | 派生読みと手順固定化 | 大技の合間の手癖被弾 | 無量弾き→パリィの交互手順固定 |
以上の観点を踏まえてルートを俯瞰し、練習すべき操作を前倒しで仕上げると、序盤から終盤までの詰まりを横断的に減らせます。チャートは固定ではなく、装備や玉石の構成次第で安全策を厚くできる点も意識すると効率が高まります。
攻略 マップ活用術
攻略マップの下部には、各エリアに配置された中ボス、アイテム、収集データの概数が表示されます。取り残しが発生しやすい縦長の区画では、視界外の上下にアイテムが配置される傾向があり、玄蝶での索敵を絡めると見落としが大幅に減ります。破壊可能な壁の裏にアイテムがあるケースも存在するため、地形の継ぎ目や不自然な空隙は積極的に攻撃して確認します。
天倉地庫のように、マーク付き装置のハッキング数が扉の開放条件になっているエリアでは、同一エリア内に装置が点在します。連続した通路の複数箇所や、エレベーター付近などにまとまっている場合もあるため、探索は往路・復路で別の視点を持たせると回収漏れを抑えられます。ボス部屋に付随するギミック(左側レーザーの奥にある装置の破壊など)は、戦闘開始前に片づけるだけで難易度が顕著に下がります。
イベント依存の扉は、鍵やスイッチではなくストーリー進行で開く設計が見られます。NPCイベントの進行度合いで開閉が変化するため、進行章とイベントの関係を簡易メモで管理し、マップ上の驚嘆符などの通知と合わせて戻るタイミングを逃さないことが大切です。
マップ探索のチェックリスト
- 玄蝶で上下視界を先読みしてからジャンプルートを決めます
- 破壊可能な壁を疑い、段差や行き止まりの直前で一撃を入れます
- ハッキング装置は数を把握し、見つけた場所を簡易記録します
- ボス前の補給オブジェや矢補充地点の位置を周回動線に組み込みます
ショートカット開通の優先順位
リスポーン地点に戻りやすいショートカットから開いていくと、往復時間が減り、死亡時の手戻りも軽減されます。特に終盤エリアは敵密度が高く、探索の余力を確保するためにも、ショートカットの開通は早めに行うのが得策です。
行き止まりを開く小技
壁登りができない状況でも、延髄蹴りで高度を稼ぐことで、通常は届かない足場に乗れる場面があります。近くにいる浮遊型や二刀流の敵の攻撃を上から踏み、反動で高度を得てジャンプと空中ダッシュを連結する手順です。敵は復活するため、失敗しても同じ手順を何度でも練習できます。
実行のコツは、踏むタイミングを敵の攻撃ヒット直前に合わせ、踏んだ直後の慣性を殺さずに最短でジャンプ入力へ移ることです。空中ダッシュは頂点の少し手前で行うと、横移動距離が最大化され、縁に指先だけ触れても登り切れる確率が高まります。
手順の例
- 敵の攻撃が当たる軌道に入り、延髄蹴りの入力を準備します
- 攻撃のヒット直前で延髄蹴りを当てて上方に跳ね上がります
- すぐにジャンプを追加し、頂点手前で空中ダッシュへ接続します
- 届かない場合は、踏み位置を半キャラ分だけ前後に調整して再試行します
この小技は、近道の開通や隠しアイテムの回収だけでなく、ボス戦の攻撃回避や反撃開始位置の調整にも応用が利きます。慣れると探索と戦闘の双方で選択肢が増え、進行の自由度が上がります。
玉石のおすすめ
玉石はビルドの方向性を明確にし、戦闘の再現性を高めます。汎用構成としてハリネズミ玉、速薬玉、身代わり玉は優先度が高く、被弾時の立て直しや継戦能力を底上げできます。受け流し玉はノックバックを抑え、第2形態以降の押し返しに強く、間合い維持の安定に寄与します。剣気玉は三元剣の3段目を強化し、確定反撃の火力を底上げできます。
滞空の無量弾きを多用する戦闘(例:易公の各段)では、速落玉の採用で着地までのタイムロスを短縮し、次の対処に間に合う場面が増えます。奉還玉は無量弾き時の内傷カウンターを狙う構成ですが、カウンター偏重で被弾リスクが積み上がるため、矢の中断や溜め攻撃による確定反撃と組み合わせ、リズムを崩さない運用を心がけます。
目的別の玉石構成(参考表)
| 目的 | 推奨玉石 | 運用の狙い |
|---|---|---|
| 安定周回 | ハリネズミ玉、速薬玉、身代わり玉、受け流し玉 | 被弾時の立て直しと間合い維持の両立 |
| 対ボス汎用 | ハリネズミ玉、速薬玉、身代わり玉、剣気玉 | 確定反撃の火力と復帰力の両建て |
| 滞空無量弾き重視 | 速落玉、身代わり玉、速薬玉、剣気玉 | 着地短縮で次アクションに接続 |
| カウンター特化 | 奉還玉、速薬玉、剣気玉、受け流し玉 | 無量弾き起点で内傷を蓄積し短期決着 |
玉石は強みと弱みが表裏一体です。例えばカウンター特化は噛み合うと短期決着が狙えますが、初動の見誤りで被弾が連鎖しやすくなります。周回や初見攻略では安定構成、ボス再戦では火力寄せ、といった使い分けが現実的です。装備の更新に合わせて、確定反撃が取れる場面を事前に洗い出しておくと、同じ構成でも効果が大きく変わります。
稼ぎの効率化
周回効率を高めるには、復活が早い敵が密集する区画で動線(スタート地点から撃破、補給、周回再開までの経路)を固定し、パリィ主体で安全に倒すループを作ることが近道です。射撃で行動を中断させてからの確定反撃や、無量弾きによる大ダメージをパターン化すると、被弾が減り、修復や回収に割く時間も短縮されます。
目安として、1サイクルあたり45〜90秒で完結するルートはテンポがよく、3〜5周を通して集中力を維持しやすい傾向があります。逆に2分を超える長尺ルートは一度のミスで収支が崩れやすいため、敵数が多くてもカットして短い周回に分割した方が成果が安定します。
ボス直前のエリアは敵の構成が強化される一方、リスポーン地点から近いことが多く、往復時間が短いので周回に向いています。弓の補充や回復オブジェの位置をルート上に組み込めば、リソース切れによる中断を回避できます。補充ポイントが遠い場合は、危険行動の初動に限定して矢を使い、パリィや踏みを優先することで弾数の浪費を抑えられます。
稼ぎルートの品質は、時間当たりの撃破数だけでなく、死亡率と移動距離の少なさで評価します。初期設計では、以下の指標で簡易的にテストすると比較が容易です。
- 1周の平均時間と最大時間(ブレ幅が小さいほど良好)
- 被弾回数と回復回数(回復を挟むほど周回時間が延びます)
- 事故要因(狭所での多段ヒット、射撃重ね、落下など)の頻度
- 補充ポイントまでの距離と通過頻度(弓・回復の安定供給)
パリィ主体のループは、敵の攻撃合図(効果音、赤攻撃の発色、タメ動作)を起点に入力を合わせるだけで成立します。無量弾きが通る相手は、溜め始動の“赤”に入力を合わせる手順を固定化し、成功後は確定の反撃コンボか呪符でリターンを最大化します。複数体に囲まれる区画では、最初の1体を矢で止めて数的有利を作るだけで、被弾率が大きく下がります。
レベル上げ指針
レベル上げは、ボス戦の壁に対して必要最小限で調整する方が時間対効果に優れます。まず玉石の組み合わせ、矢の使い所、パリィ精度など操作面の再現性を整え、それでも足りないと感じる要素に限定して底上げする考え方が効率的です。攻撃一辺倒ではなく、回復速度や行動中断の取り回しを強化することで、総合的な勝率が上がります。
判断基準として、同一ボスに連続10戦挑み、毎回の削り量と被弾の型がほぼ一致しているのに削り切れない場合は、純粋に数字が不足している可能性が高く、レベル上げの投入時期と言えます。逆に、被弾要因が毎回異なる場合は、育成よりも手順の固定と判断の整理を優先した方が短時間で改善します。
周回時は、パリィで確実に倒せる敵を主軸に選ぶと、時間当たりの成果が安定します。敵の密度、移動距離、補給ポイントの有無を比較し、1サイクルに要する時間を少しずつ短縮していけば、反復回数を増やさずに必要値へ届きます。ビルド変更の影響を把握するため、玉石を1点だけ入れ替えて前後の平均周回時間を3〜5周で比較すると、伸びしろの有無を定量的に判断できます。
終盤のレベル設計は、ボスごとの要求精度に合わせた“安全マージン”を持たせると安定します。具体的には、危険行動に矢を差し込んで中断し、回復やバフの再展開を許さないだけのリソース管理を優先します。削り時間が長くなるほど被弾機会が増えるため、確定反撃の火力を上げられる玉石(例:剣気玉)や、立て直し性能を底上げする玉石(例:身代わり玉、速薬玉)を段階的に導入するのが現実的です。
九日ナインソール 攻略 ボス別対策集
- 蚨蝶 攻略の要点
- せつぜん 攻略要点
- 風氏の対処法
- 易公の立ち回り
- 真エンド到達条件
- 攻略 ボスの総括
蚨蝶 攻略の要点
蚨蝶の本質は、分身を伴う多段圧力の整理と、本体スタンを起点に盤面をリセットするマネジメントにあります。攻撃パターンそのものは大きく変化せず、フェーズ進行とともに“密度”が増す構造のため、対処の手順を固定できれば難度が一段下がります。
第1形態は本体のみの連係です。真横や斜め上からのダッシュ攻撃はパリィで受け、水色の追尾弾はパリィで処理すると弾抜けの事故が減ります。赤い水平弾はダッシュで軸を外すのが安全で、パリィに固執するより被弾が減ります。ここでリズム(入力間隔)を掴んでおくと、後続フェーズでも同じテンポで捌けます。
第2形態は分身が連続で攻め、認識負荷が上がります。見分けに迷うときは、お札を使って分身を消し、視界情報を減らしてから本体に溜めや札を合わせると主導権を取り戻せます。スタンを発生させると、分身が展開中の攻撃も消えるため、攻めと守りの切り替えが容易になります。
第3形態は見た目に差が出るため、本体の判別がしやすくなります。分身の突進二連の後に地面破壊が続く大技は、分身パリィ、分身パリィ、ダッシュ回避の三拍子で処理するのが安定ルートです。上空での溜め行動は、左右からの突進をパリィした直後に回避へ移行すると、被弾の可能性が低い帯に入れます。以上の流れから、常にスタンをトリガーに盤面を初期化し、本体に確実に触ることが勝ち筋だと言えます。
よくあるつまずきと修正ポイント
- 分身に視線を奪われ本体を逃す:お札でノイズを消し、ターゲットを単純化します
- 水平弾に対して過剰にパリィを狙う:ダッシュでラインを外す方が事故率が低下します
- スタン後に攻撃を散らす:本体への確定反撃を最優先し、分身は視界から外します
フェーズ別の要点整理(参考表)
| フェーズ | 優先行動 | 失敗しやすい点 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| 第1形態 | 追尾弾はパリィ処理し、赤水平弾はダッシュ回避に統一 | 弾種ごとに判断がぶれて被弾が増える | 追尾=パリィ、水平=回避のルールを固定して迷いをなくす |
| 第2形態 | お札で分身を消し視界を整理してから本体にスタン | 本体を見誤り火力が分散し長期戦化 | 先に札で盤面を減らし、札後は必ず本体へ溜め攻撃で確定を取る |
| 第3形態 | 分身判別後の大技はパリィ二回から回避の三拍子 | 三拍子のテンポが崩れて被弾が連鎖 | 先にパリィ二回の間隔を練習で固定化し、その後の回避入力を遅らせず接続する |
せつぜん 攻略要点
戦闘の手触りが大きく変化する相手で、事前弱体化の有無が難易度を左右します。バトル前に隣接する装置へ遺伝子除去剤を投入すると弱体化が適用され、咳き込みによる長い硬直など明確な攻め時が生まれます。除去剤は下層の鍵付き部屋に配置されているため、探索の導線上で確実に回収してから挑む計画が安定につながります。
第1段階は、投げナイフの反射と槍系モーションの見極めが要です。投げナイフはパリィで跳ね返し、槍の二段から赤突きは二度パリィした後に踏みで締める手順を固定します。薙刀の溜めは見た目の溜め動作に合わせた無量弾きが有効で、成功時は確定反撃へ直結します。地雷撒き→バリア展開は、溜め攻撃でバリアを破壊し、回復行動を阻止して長期戦化を防ぎます。
第2段階は第1段階の強化版で、速度と手数が増します。弱体化の効果が切れた直後は押し返されやすいため、赤行動の初動に矢を差し込んで行動を中断させ、再び距離とテンポを取り戻します。ここでの目的は無理に削ることではなく、危険行動を“止める”ことで自分のリズムへ戻すことです。
第3段階は連携の密度が最大化しますが、合図は一貫しています。ダメージレースを避け、パリィと無量弾きで相手の手数を反転させる姿勢が勝ち筋です。弱体化なしの挑戦では、視界と入力の負荷が上がるため、矢の使用は赤の初動と回復準備の気配へのピンポイント運用に絞り、被弾の連鎖を断ち切ります。要するに、各段階で“止めるべき技”を先に決め、そのための資源(矢・溜め・スタミナ)を温存する設計が、最短の安定化に直結します。
風氏の対処法
伏羲と女媧の二体連携が特徴で、とりわけ第2形態の同時圧力が山場です。基本は、爪の振り下ろしや飛び込みをパリィで受け、赤の溜めに対して無量弾きで反撃へ転じる流れを繰り返します。初期矢の穿雲神矢は行動中断とスタンを兼ねるため、危険行動の初動に合わせて節約運用すると、事故要因を計画的に消せます。
第2形態では、女媧の蛇や連続爆破、槍の投射が重なりやすく、要無量弾きの直前にナイフ二本が重なることがあります。この場合はナイフをパリィで処理した直後に溜めを開始しても間に合うため、動揺せず“パリィ→溜め→無量弾き”の順番を崩さないことが大切です。ピンクの蛇は軌道上で避けるしかなく、ピンクの球は踏みで消せるため、受ける対象と避ける対象を事前に決めて視線の配分を固定します。
蛇のパターンは、画面端から順番に迫るタイプ、上空から等間隔で降りるタイプ、地面水平に往復するタイプの三種が核です。水平蛇にはジャンプとダッシュを組み合わせ、当たり判定のない通過帯を維持します。矢での行動中断は切り札として温存し、パリィで取れる攻撃を確実に取り切るほうが、終盤での余力確保に直結します。以上を踏まえると、第2形態は“整理のフェーズ”と捉え、視覚情報をルール化して処理順を明確にする発想が有効です。
易公の立ち回り
設計の緻密さが際立つボスで、攻撃頻度、派生の多彩さ、対処の選択肢の三点が核心です。第1形態では、二連斬り、二連・三連突き、すれ違い居合などの型を個別に認識し、ダッシュお札貼りは踏みで制止します。気弾叩きつけは無量弾きが通りやすく、刀の効果音や目を見開く瞬間といった視覚・聴覚の合図を“同時に”手掛かりにするとタイミングが安定します。
第2形態では、大技連携が本格化します。居合の赤から居合二回、続いて赤縦斬りまたはすれ違い居合に派生する一連は、無量弾きとパリィを交互に当てる定型手順で受け切れます。ダッシュお札貼りからの分岐は、ジャンプ斬りが一回か二回かで後続が変わり、気弾叩きつけへ続くときは二度目の無量弾きの方が取りやすい傾向があります。パターン認識を“音と動きのセット”で覚えると、視線が忙しい状況でも入力がぶれにくくなります。
第3形態は全画面二回斬りから横一閃という強力な追い打ちが加わります。空中で二回パリィし、わずかに溜めてからのパリィで横一閃のタイミングに合わせる手順を固定化します。横一閃が赤の場合は、先にジャンプで高度を確保し、無量弾きと回避を組み合わせて安全帯に入ります。矢の中断は叩きつけや構えの初動に差し込むと、呪符での反撃機会が生まれ、ダメージ効率が大きく変わります。
推奨構成と運用の目安(参考表)
| 要素 | 推奨例 | 狙い |
|---|---|---|
| 玉石 | ハリネズミ玉、速薬玉、身代わり玉、速落玉 | 立て直し性能の確保と着地テンポの最適化 |
| 呪符 | 行雲流水(または収放自如) | 行動中断後に確定ダメージへ直結 |
| 矢運用 | 中断用を温存し補充ループを意識 | 事故場面の強制停止と長期戦の安定化 |
以上の点を踏まえると、第2形態で派生の核を掴み、第3形態では全画面と横一閃の手順を固定化することで、被弾の揺らぎが減り、勝率が着実に上がります。学習の順序は“認識→手順化→火力化”の三段階で進めると、再戦でも再現性が高くなります。
真エンド到達条件
真エンドへの到達は、イベントと収集の同時管理が前提になります。道教石窟の小部屋では、装置を起動して出現する敵の攻撃に完璧なパリィを連続して決めると、右側の仕切りが開き、棺から人物のホログラムが現れます。同様の部屋で所定数をそろえると、彼らが集う場所で変化が発生するため、探索の段階でマーカーや簡易メモを併用し、進捗を可視化しておくと取り逃しを防げます。
一部エリア最上部の扉は、対応するNPCイベントの進行によって開くタイミングが到来します。鍵やスイッチを探すよりも、イベントの発火条件(会話の進行や到達章など)を優先して満たす運びが有効です。終盤の分岐では、ボス挙動や形態数が変化するケースがあるため、リソース配分や装備構成を前提として見直し、長期戦に耐える補給動線を設計します。
取り逃し対策として、攻略マップ下部の指標(中ボス数・アイテム数・収集データ数)を定期的に確認し、不足分を埋めてから終盤へ進むのが堅実です。戦闘力の強化だけでは到達率が頭打ちになる場面があるため、イベントの消化順と探索ルートの最適化を前倒しで進める計画が近道となります。
九日ナインソール 攻略 ボスの総括
- 攻略チャートは中盤の寄り道管理が進行安定の鍵
- 攻略マップ指標で未取得を埋めて詰まりを回避
- 玉石は汎用三種に速落玉を加える構成が堅実
- 稼ぎは復活の早い区画でループ動線を固定
- レベル上げは不足分の底上げに限定して時短
- 蚨蝶はスタンで分身の圧力を切り崩して主導
- せつぜんは遺伝子除去剤の弱体化で安定攻略
- 風氏は第2形態の多重圧力を役割分担で処理
- 易公は第2形態の派生把握が勝率上昇の分岐
- 全画面攻撃は空中二度の受けで横一閃に接続
- 矢の中断は事故回避の切り札として温存運用
- 無量弾きのタイミングは音と挙動の二重確認
- イベント依存の扉は進行時期を逃さず管理
- 道教石窟の小部屋は完璧パリィで仕掛け進行
- ナインソール 攻略 ボスは再現性の型作りが要