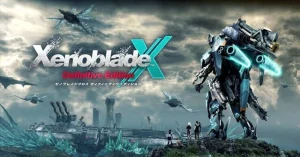HADES(ハデス)の攻略ビルドを探している読者が、何から手を付ければよいか迷いやすいのは自然なことです。最強を目指すうえで、おすすめ武器の選定や最強武器の活かし方、拳ビルドと弓ビルドの立ち回り、そして初心者がつまずきやすい強化計画まで、判断材料は多岐にわたります。各武器の態のおすすめ構成を整理し、ティタンの血の投資先を明確化することで、安定して勝率を高められます。本記事では、実用的な視点でビルドの考え方と運用手順を体系的に解説します。
- HADES(ハデス)攻略ビルドの全体像と考え方
- 初心者向けの強化優先度と失敗しにくい進め方
- 拳ビルドと弓ビルドを軸にした実戦運用
- ティタンの血の投資配分と長期的な育成計画
HADES(ハデス) 攻略ビルドの基本ポイント
- 初心者が理解すべき基礎知識
- ティタンの血の効率的な使い方
- おすすめ武器の選び方の基準
- 拳ビルドで安定した立ち回り
- 弓ビルドで火力を引き出す方法
初心者が理解すべき基礎知識
攻略を安定させる近道は、ゲーム全体の構造とビルド設計の原理を早い段階で押さえることにあります。各エリアや部屋の選択、恩恵や槌の出現はランダムですが、判断基準をあらかじめ用意しておけば、毎回のランで選択のブレが減り、勝率が段階的に伸びます。以下では、序盤から役立つ設計思想と操作の軸を整理します。
ゲーム構造と意思決定フロー
部屋報酬のアイコンを確認し、主力手段の強化につながる選択を優先します。主力は「攻撃」「特殊攻撃」「キャスト」「ダッシュ攻撃」「神の加護(ゲージ技)」のいずれか一つに絞ると扱いやすく、以後の恩恵や槌はその主力を伸ばすものを中心に取得します。主力が定まると、補助の役割(防御・移動・範囲処理・単体DPS)の取捨選択も明確になります。
夜の鏡の優先度と理由
夜の鏡はビルドとは独立した恒常強化で、攻略の土台になります。序盤は生存と操作性を優先し、火力系は中盤以降に伸ばす構成が安定します。
| 強化カテゴリ | 推奨優先度 | ねらい | 補足 |
|---|---|---|---|
| 体力上限・復活回数 | 高 | 被弾時の立て直し | ボス戦での再挑戦余地を確保 |
| ダッシュ強化 | 高 | 無敵時間の活用 | 位置取りと攻撃回避の両立 |
| キャスト装填・回収 | 中 | 継続DPSとギミック対応 | 主力をキャストに据える場合は優先度上昇 |
| ゴールド・報酬効率 | 中 | 店・冥夜の取引を活用 | 序盤は過度に伸ばしすぎない |
| クリティカル・ダメ倍率 | 中〜低 | 上振れ火力 | 生存が整ってから段階的に投資 |
記念品と恩恵の絞り込み
記念品は出現恩恵を絞る最も強力な手段です。主力の属性(会心寄り、持続ダメージ寄り、範囲寄り)に合った神を狙い、序盤の要となる恩恵を確保します。中盤以降は完成度に応じて記念品を付け替え、足りない要素(防御、範囲、単体特化)を補完します。
戦闘の役割整理と操作のコツ
主力と補助の線引きを先に決め、モーション中に被弾しにくい攻撃を軸に据えます。ダッシュには短い無敵時間があり、敵の攻撃判定に合わせてタイミングよく差し込むことで、被弾を大幅に減らせます。射程、攻撃発生、硬直の長さを常に意識し、背面や斜め方向への回り込みで安全に主力を通すのが基本です。
槌(デダルスの槌)で方向性を固定
槌の効果はビルドの完成形を大きく左右します。主力の短所を補い長所を伸ばす効果(攻撃範囲拡張、発生短縮、ヒット数増加、チャージ短縮など)を最優先し、噛み合わない候補は潔く見送ります。槌1個目でビルドの輪郭を固め、2個目で弱点を埋める発想が再現性を高めます。
バージョン差異への備え
仕様はアップデートで調整されることがあります。プレイ中のバージョンに合わせて最新の変更点を確認し、強化や恩恵の優先順位を微調整してください。
ティタンの血の効率的な使い方
ティタンの血は武器の態(アスペクト)を解放・強化する希少資源です。配分の巧拙が攻略体験を大きく左右するため、投資の順番と止め時を意識した計画が求められます。
集中投資と止め時の設計
最初は使用頻度の高い武器を1種選び、主力の態を集中的に強化します。段階が上がるほど要求数は増えるため、体感の伸びが大きい中位段階で一旦停止し、2本目の主力に分散するのが効率的です。一本化で確実な強さを先に得てから、サブ武器の完成度を引き上げると、ラン全体の成功率が底上げされます。
入手計画と周回設計
入手機会は周回報酬や特定の交換・挑戦達成などに限られます。各エリアの進行速度と被弾率を鑑み、安定ルートでの周回を優先すると回収効率が上がります。高難度条件の導入は、主力ビルドが十分に整ってから段階的に行うと安定します。
投資戦略の例
| フェーズ | 投資対象 | 狙い | 判断基準 |
|---|---|---|---|
| 序盤 | メイン武器の主力態 | 早期に勝てる武器を確立 | 操作負荷が低く事故が少ない |
| 中盤 | メインの完遂+サブ着手 | 構成の穴埋めと選択肢拡張 | 体感伸びが鈍化したら別武器へ |
| 終盤 | サブの仕上げ | 高難度・実績回収対応 | ボス耐性や範囲処理を補強 |
よくあるつまずきと回避策
複数武器に薄く投資して火力がどれも中途半端になる、主力と噛み合わない態を伸ばしてしまう、といった行き詰まりが典型例です。主力の攻撃テンポや到達距離、槌・恩恵の当たり率といった“システム的相性”を基準に見直すと、投資効率が回復します。
おすすめ武器の選び方の基準
おすすめ武器は個々の好みだけでなく、システム上の相性と再現性から評価することで、客観的に選定できます。以下の基準を使うと、環境や腕前が変わっても最適解を導きやすくなります。
評価指標のフレームワーク
- 生存性:回避行動中の安全性、攻撃後の隙の短さ、射程と位置取りの自由度
- 継続火力:平均DPSの出しやすさ、動きながら火力を維持できるか
- バースト力:ボスの硬直に高火力を差し込めるか、チャージや設置の取り回し
- 槌との相性:当たり効果の多さ、外れを引いた際の代替ルートの有無
- 恩恵シナジー:状態異常や会心系との噛み合い、発動条件の緩さ
- 操作負荷:要求入力の忙しさ、視認性、エイム精度の要求度
- 難所適性:群れ処理、弾幕回避、狭所・広所での立ち回りやすさ
チェックリストでの実用選定
次の問いに多く「はい」と答えられる武器ほど、攻略での再現性が高いと判断できます。
・動きながら安全にダメージを継続できますか
・槌の当たりを複数パターン想定できますか
・主力に合う恩恵が2神以上思い当たりますか
・ボスと雑魚の両面で火力を切り替えられますか
・チャージや硬直のフォロー手段が用意できますか
例示的な評価の考え方
近接で手数を出す武器は、連打や多段ヒットと相性の良い恩恵・槌を揃えると継続火力が安定します。一方、間合い管理を主軸にする武器は、弱化などの防御的シナジーで被弾を抑えつつ、チャージ短縮や会心寄せでバースト力を確保すると終盤まで失速しにくくなります。結果として「おすすめ武器」は単純な最大ダメージではなく、事故を避けやすい設計と選択肢の広さで評価するのが実務的です。
拳ビルドで安定した立ち回り
近接で最速クラスの手数と機動力を両立できるのが拳ビルドの魅力です。要は「短い隙で差し込む→即離脱」を反復し、被弾リスクを最小化しながらヒット数を稼ぐ設計にまとめます。多段ヒットの性質上、弱化や中毒、破滅といった継続・追撃系の効果と親和性が高く、ヒット数×付与維持時間の積で実効DPSが伸びやすいのが特徴です。
加えて、ダッシュ無敵を絡めた当て逃げは、敵の予備動作の終わり際に差し込むと成功率が上がります。正面からの正対より、斜めから踏み込み背面を取る角度進入を習慣化すると、広範囲攻撃の巻き込みを避けやすくなります。
コア設計の考え方
- 主力は通常攻撃を核に据え、特殊攻撃は状況対応(ノックバック・間合い調整)に回します
- キャストは継続付与や弱点化の維持を担当し、ダッシュ攻撃は差し込みの起点として使います
- 槌は「発生短縮」「攻撃範囲の拡大」「ヒット数の増加」など、短所補填と長所伸長の両面で評価します
インプットのルーチン化
1サイクルを「ダッシュ進入→1〜2手で確実に当てる→ダッシュ離脱→軸ずらし→再進入」と定義し、被弾の起点になりやすい硬直を常にダッシュで断ち切ります。敵弾が多い場面では、ダッシュ離脱後に横回避を1テンポ挟み、射線上から外れてから再進入すると安定します。
状態異常とのシナジー
ヒット数が多いほど付与や再付与が安定し、弱化で被ダメージを抑えつつ、破滅・中毒で時間あたりの総与ダメージが積み上がります。付与維持を主眼に「当て続ける時間」ではなく「維持に必要な最低限の当て直し回数」で考えると、無駄な滞在が減り被弾も減少します。
序盤の組み立て
開始直後は生存設計を先に固め、扱いやすさを最優先します。具体的には、ダッシュの強化や被弾軽減、回復機会の確保といった防御寄りの恩恵を先行させ、攻撃面はヒット数に連動して効果が伸びるものを選びます。序盤で「倒し切る前に被弾して崩れる」事態を避けるだけで勝率が目に見えて変わります。
優先すべき常設強化と理由
- ダッシュ強化:短い無敵を活かして差し込みと離脱を繋げられます。入力受付の猶予が広がるため、ミスが減ります
- 体力上限・復活:ボス戦の再試行性が増し、学習コストが下がります
- キャスト装填数:拳の手数に継続ダメージや弱点化を重ねやすくなります
槌と恩恵の方針
槌は「攻撃速度の底上げ」「当たり判定の拡張」「コンボ中の移動性向上」を優先します。恩恵は弱化・破滅・中毒・感電など、当て逃げのサイクルで自然に効果を稼げるものから取り込みます。序盤は一極集中で主軸を決め、広く浅く手を出さないことが完成を早めます。
失敗しにくい部屋選択
報酬は主力の完成に直結するアイコンを優先し、ショップや回復は「被弾が増えた後」に寄せます。強化の噛み合いが薄い場合は、強敵部屋を避けて安定ルートを取り、主力がそろうまでリスクを抑える判断が有効です。
中盤〜終盤の強化
中盤以降は、完成した主軸に高効率の状態や追撃を重ね、対ボスのバーストと対集団の制圧を両立させます。拳は滞在時間が伸びるほど危険が増すため、「短時間で必要効果を更新→離脱」を徹底し、被弾の芽を潰します。
ボス向け最適化
- 予備動作の終端に差し込む:安全時間に合わせて2〜3入力で確実に刻みます
- 硬直短縮と範囲拡張の槌:差し込み回数を増やし、当て損じを減らします
- 会心・追撃を重ねる:短時間での最大伸びを狙い、長居を回避します
集団処理の工夫
ノックバックや小範囲制圧を一時的に組み込み、密着事故を抑えます。カメラ外からの突進が多い場面では、斜め後退で集団を細長く並べ、当たり判定をまとめてから差し込むと被弾が減ります。
バージョン差異への配慮
武器性能や一部効果はアップデートで調整されることがあります。運用の細部はプレイ中のビルドと現行バージョンに合わせて微調整してください。
弓ビルドで火力を引き出す方法
遠距離から確実に削る弓は、チャージ時間と位置取りの管理が要になります。チャージショットでの単発高火力か、特殊攻撃連射による擬似的な継戦力か、どちらを主軸に据えるかを先に決めると、槌と恩恵の選別が明確になります。会心寄せ、破滅の時間差追撃、感電の再付与など、単発の重さを増幅する系統と好相性です。
チャージショット軸
- 射線の確保を最優先し、障害物越しの撃ち下ろしや斜線ずらしを用います
- チャージ短縮・弱化付与・会心強化の順で伸ばし、短い隙で確定打を通します
- 被弾源になりやすい足止め時間は、ダッシュキャンセルや段差・障害物の活用で圧縮します
特殊連射軸
- 射程と拡散を利用して群れに面処理を行い、危険個体のみチャージショットで仕留めます
- 感電・破滅・凍結など、当て続けで価値が増す効果を優先します
- 槌は「硬直軽減」「弾速・範囲拡大」系を選び、当たり前に当てられる状況を作ります
立ち回りのコツ
弓の真価は「撃てる姿勢」を維持できるかで決まります。足を止める時間を必要最小限に抑え、敵の詰め寄り角度を制御しながら、常に安全な射線を構築します。
共通原則
- 射線の先に逃げ場を作らない:後退しつつ撃つより、横移動で射線から外れて再配置します
- 予備動作に合わせて溜め始める:硬直の終わり際に放つと被弾リスクが低下します
- 角度管理:敵の直進軸をずらし、横からの矢で確定を取ります
ボス戦の運用
モーションの周期に合わせて「移動→チャージ→発射→移動」を一定テンポで回し、欲張らずに1サイクル1発を徹底します。設置や持続の効果を先に展開しておくと、チャージの待ち時間にもダメージが途切れにくくなります。
槌と恩恵の最終調整
不足しているのが「当てやすさ」か「一撃の伸び」かを見極め、前者なら硬直・弾速・範囲、後者なら会心・弱化・追撃を追加します。終盤は被弾1回のコストが跳ね上がるため、火力よりもまず命中安定と回避余裕の確保に寄せる判断が、最終勝率の底上げにつながります。
HADES(ハデス)攻略ビルド別の強化と応用
- 最強と呼ばれるビルドの特徴
- 最強武器を活かした戦い方
- 状態おすすめを踏まえた戦略
- シチュエーション別おすすめ武器
- 中盤以降に強い拳ビルドの応用
- 終盤向け弓ビルドの工夫
- まとめ ハデス 攻略 ビルドの最適解
最強と呼ばれるビルドの特徴
高難度でも崩れにくい構成には、いくつかの普遍的な設計原則があります。個々の武器や好みが違っても、これらの原則に沿って積み上げることで、勝率と再現性が着実に向上します。
防御設計が先、火力は後から積む
ダメージを受けにくい形を先に作ると、学習コストが下がり全体DPSも上がります。ダッシュ強化や被ダメージ軽減、敵弱体化の付与など、被弾を減らす要素を土台にします。ここができているビルドは、難所での事故が少なく、ボスのギミック処理にも余裕が生まれます。
単体DPSと範囲処理の両立
最強格のビルドは、ボスに対する瞬間火力と、雑魚戦の制圧力を同時に確保します。具体的には、主力攻撃を単体特化に定めつつ、特殊攻撃やキャストで範囲をカバーする二層構造にすると、場面の切替に強くなります。単体向けと範囲向けの役割分担が明確だと、選択と集中ができ、強化の無駄が生まれにくくなります。
乱数依存を減らす再現性設計
恩恵や槌の引きに左右されすぎないのも強さの条件です。複数の当たりルート(代替シナジー)を用意し、どれかが欠けても成立する構成にしておくと、毎ランの完成確率が上がります。たとえば、会心寄せが引けない場合の継続ダメージ寄せ、チャージ短縮が来ない場合のヒット数増加といった代替案を事前に決めておきます。
投資効率の良い態を選ぶ
ティタンの血の要求量は段階が進むほど増えます。伸びが体感しやすい中位段階まで主力態を優先し、その後はサブ武器に投資してルートの幅を持たせると、総合勝率が上がります。単に最大値を追うのではなく、到達しやすい強さを重視するのが現実的です。
バージョン差異への配慮
パッチで各種性能が調整されることがあります。現行バージョンの変更点を確認し、優先順位を微調整してください。
最強武器を活かした戦い方
候補とされる武器は環境で変動しますが、最大限に引き出すための運用原則は共通です。主力を明確に据え、短所をシステム側で補い、火力はシナジーで底上げします。
主力固定とテンポ設計
主軸を攻撃、特殊、キャストのいずれかに固定し、残りは補助に回します。主力の発生・硬直・到達距離を基準に「当てる時間」「離脱の余白」を設計し、ダッシュ無敵で硬直を区切るテンポを作ります。ここで欲張らず、1サイクルで確実に与えられるダメージ量を目安化すると、被弾が減り総合効率が上がります。
槌は短所補填を最優先
チャージが重いなら短縮、間合いが足りないなら範囲拡張、ヒット数が欲しいなら多段化といった具合に、主力の弱点をピンポイントで解消します。1個目の槌で方向性を固定し、2個目で当てやすさや安定性を強化すると、完成度が一段上がります。
恩恵はトリガーと連携で伸ばす
会心や弱化、継続ダメージ、追撃などは、単体ではなく連携で価値が高まります。例えば、弱化で被弾を抑えつつ、破滅や感電のような時間差ダメージを重ねると、短時間の差し込みでもダメージが残り、離脱の安全性が増します。発動条件が緩く、主力のテンポと噛み合うものを優先します。
ボスと雑魚での切替
ボスには硬直タイミングにバーストを合わせ、雑魚戦では範囲とノックバックで密着事故を抑えます。切替の軸は「主力そのものを変える」のではなく、「同じ主力に付随する補助スキルを入れ替える」イメージにすると、手癖が崩れず安定します。
状態おすすめを踏まえた戦略
状態異常は制圧力と継続火力の源泉であり、主力のテンポと一致しているほど効果が指数的に伸びます。名称は異なっても、役割はおおむね次の五系統に整理できます。
役割と選定の考え方
- 弱化系:被ダメージの抑制と確定ダメージの底上げに寄与します。間合い管理や単発高火力と好相性です
- 破滅系:時間差の追撃を発生させ、手数武器で特に伸びます
- 中毒系:多段ヒットで維持が容易になり、群れ処理にも波及します
- 感電系:敵の行動タイミングに合わせて自動的に追加ダメージが発生し、当て逃げと噛み合います
- 凍結系:拘束により危険個体の処理が安全になり、遠距離・チャージ系の安定性が向上します
以下は代表的な相性の整理です。
| 状態異常 | 相性が良い攻撃傾向 | 立ち回りの要点 |
|---|---|---|
| 弱化 | 単発高威力、間合い管理型 | 被弾抑制と同時に主力の確定火力を底上げ |
| 破滅 | 手数多め、継続ヒット | 時間差追撃で総合DPSが伸びやすい |
| 中毒 | 多段ヒット、連打系 | 付与維持で安定火力、群れ処理も向上 |
| 感電 | 回避主体、ヒットアンドアウェイ | 敵行動に合わせて安全にダメージを重ねる |
| 凍結 | 距離戦、足止め重視 | 危険敵の拘束で事故率を大幅に低減 |
意思決定フロー
- 主力のテンポを確認する(連打型か、単発型か、設置型か)
- 生存性に直結する弱化や拘束を先に確保する
- 追撃や継続系でDPSを底上げし、足りない側面を補う
- 代替ルートを2本用意し、引き負け時の完成度を担保する
以上の点を踏まえると、拳のような連打武器は中毒や破滅で伸びやすく、弓のような間合い武器は弱化や凍結を重ねると安定性が増します。状態選定は主力の性質から逆算し、当て直し頻度と離脱余白を基準に最適化すると、総合的な勝率が引き上がります。
シチュエーション別おすすめ武器
エリア構造や敵の組成によって、同じ武器でも評価は大きく変わります。開けた地形では射線の確保が容易な遠距離・設置系が優位に立ちやすく、遮蔽物が多い狭所では踏み込みと離脱が速い近接・機動系が安定します。移動しながら攻撃できる構成は、弾幕密度が高い局面でも姿勢を崩しにくく、被弾要因の多くを事前に排除できます。以下に、代表的な状況ごとの適性を整理します。
地形・敵構成別の適性早見表
| シチュエーション | 推奨アーキタイプ | 主力運用の軸 | 補助の役割 | 主なリスク | 具体的な対策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開けた地形(広い円形・直線) | 遠距離・チャージ型、設置型 | 射線を長時間確保して確定打 | ノックバック・足止めで間合い維持 | 溜め中の被弾 | チャージ短縮、弱化付与で安全時間を拡張 |
| 狭所・遮蔽物多め | 近接・手数型、機動型 | 当て逃げでヒット数を稼ぐ | 範囲小技で密着事故を抑制 | 多方向からの挟み込み | 範囲拡張の槌、回避強化で斜め離脱を徹底 |
| 弾幕密度が高い群れ | 設置・持続ダメージ型 | 通路制圧で敵の進路を限定 | ダッシュ無敵と横移動で再配置 | 視界外突進 | ノックバック、足止め、壁利用で列を細くする |
| 機動力の高い精鋭混成 | 近接・遠距離のハイブリッド | 危険個体のみ単発高火力で処理 | 広域牽制で雑魚の足を止める | 目標の取り違え | ターゲット固定を優先、主力の切替は最小限 |
ボス戦では、相手ごとの無敵時間や攻撃後硬直の長さを把握し、確定で通るタイミングに主力を差し込みます。単発型は機会を一点集中で最大化し、連打型は離脱を前提に短サイクルで効果を更新します。高難度条件下では、理論上の最大DPSよりも事故を減らす設計が勝率を押し上げます。ゲーム内の調整により各武器・恩恵の性能は更新されるため、最新の変更点を確認して優先順位を微調整してください。
中盤以降に強い拳ビルドの応用
中盤以降の拳ビルドは、機動力と継続火力の両立がテーマになります。ヒット数を最大化するほど状態付与や追撃が伸びますが、滞在時間が長いほど被弾リスクも上がるため、短サイクルでの更新と離脱をセットにした設計が有効です。
攻撃サイクルの最適化
「ダッシュ進入→通常1〜2回→特殊で姿勢調整→ダッシュ離脱」を基本単位にし、1サイクルの入力数を固定化します。硬直が長いモーションは斜め進入や背面取りで当て、離脱は必ず横移動を噛ませて射線から外れます。群れ相手では、先にノックバックや小範囲の押し返しを入れて列を細くし、巻き込み事故を抑えます。
槌の選択優先度
- 第一優先:発生短縮・攻撃範囲拡大・ヒット数増加
- 第二優先:移動中の攻撃安定化(滑走、追尾補助など)
- 第三優先:チャージ短縮や硬直軽減などの操作性強化
1つ目の槌で方向性を固定し、2つ目で当てやすさと安全余白を広げると、完成度が一段上がります。
状態付与と会心の組み合わせ
中毒や破滅などの時間差ダメージは、拳の多段ヒットと好相性です。弱化を先に重ねて被ダメージを抑え、短い接触で効果を更新し続けると、滞在せずとも総与ダメージが積み上がります。会心寄せは瞬間火力を押し上げますが、当て直し頻度が下がると維持が難しくなるため、更新タイミングをサイクルに組み込みます。
耐久と位置取り
被ダメージ軽減や回復機会の確保は、ボス戦の再試行性と学習効率を高めます。危険攻撃は正面から受けず、角度をずらして側面から差し込みます。視界外の突進が多いフェーズでは、斜め後退でラインを細長く整え、まとめて当てる場面を作ると安定します。
終盤向け弓ビルドの工夫
終盤の弓は、距離とチャージの管理精度が勝敗を左右します。チャージショット主体なら溜め時間を短縮し、特殊連射主体なら足を止める時間を極力削り、どちらの軸でも「撃てる姿勢」を維持することが要点です。
チャージ主体の強化
チャージ短縮と弱化付与、会心強化の順で伸ばすと、短い隙で確定打を通しやすくなります。障害物や段差を使って射線だけを通し、被弾源になる正面の足止めを避けます。ボス戦では、予備動作が始まった瞬間に溜めを開始し、無敵や硬直の切れ目に合わせて放つサイクルを確立します。
特殊連射主体の強化
拡散・弾速・範囲拡大の槌で面制圧能力を高め、感電や破滅、凍結といった再付与で価値が増す効果を優先します。危険個体だけはチャージショットで確実に処理し、雑魚は特殊連射で押さえる役割分担にすると、過剰な溜めによる被弾を避けられます。
終盤向けの最終調整
不足が「当てやすさ」なら硬直・弾速・範囲で補い、「一撃の伸び」なら会心・弱化・追撃で伸ばします。群れ相手には足止めやノックバックを先に展開し、射線の確保を常に最優先にします。最終局面ほど被弾1回のコストが高くなるため、火力を積みきる前に命中安定と回避余白を確保する配分が、結果として総DPSの底上げにつながります。
まとめHADES(ハデス)攻略ビルドの最適解
- 攻略は主力手段と補助の役割分担を明確化する
- 夜の鏡は生存力とダッシュ強化を優先して底上げする
- 記念品で狙いの恩恵を引き込みビルド再現性を高める
- ティタンの血は主力の態に集中投資し完成度を高める
- 槌は主力の短所補填を第一に選び総合力を底上げする
- おすすめ武器は被弾管理と恩恵親和性で評価する
- 最強の条件は単体火力と範囲処理の両立にある
- 拳ビルドは中毒や破滅と相性が良く継続火力が伸びる
- 弓ビルドは弱化や凍結で安全圏から確実に削る
- 状態異常は主力のテンポと噛み合う種類を選定する
- 序盤は扱いやすさを重視し中盤以降に伸びる構成へ移行する
- ボス戦は無敵明けや硬直に差し込み被弾を抑える
- 群れ相手は足止めと位置取りで事故率を下げる
- 高難度では削り速度より再現性の高い防御設計を優先する
- 周回では報酬計画と取りこぼし防止で成長を継続する